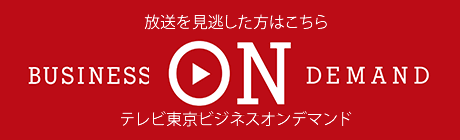テレビ東京 ガイアの夜明け
道の駅サバイバル!〜誰のためのものか?〜
夏休み真っ只中、旅の途中に、あるいは旅の目的地として「道の駅」を訪ねた人も多いはず。地域振興の目玉としても注目される「道の駅」は、今や全国1200ヶ所以上。地元の特産品販売や観光案内だけでなく、近年では防災拠点としての役割も期待されるなど、その存在感は増すばかり。しかし、盛況なイメージの裏で、およそ3割が赤字経営とも言われている。廃業に追い込まれる施設もあるなど、「格差」が広がりつつある。成功すれば”地方創生の切り札”に、失敗すれば”負の遺産”となる諸刃の剣ともいえる。自治体、事業者、住民、観光客…道の駅は誰のためのものなのか?”日本一”から赤字が続く施設まで、密着取材からその存在意義と可能性を探る。
神奈川・湘南エリアに誕生!ハイブリッド型「道の駅」とは
7月、神奈川・湘南エリアで初めてとなる道の駅「湘南ちがさき」が誕生した。江の島のある藤沢市や大仏のある鎌倉と比べてこれといった特産品がない茅ヶ崎市は、観光客が通り過ぎてしまうことが課題だった。新施設では、隠れた地元の名産品を掘り起こし、地元産の商品を6割揃える。運営するのはファーマーズ・フォレストの松本謙社長。栃木・宇都宮市の「道の駅うつのみや ろまんちっく村」を成功させるなど、客を呼ぶ道の駅づくりのプロフェッショナルだ。有機栽培で丁寧に作られた地元野菜や漁師が朝獲った魚、さらに地元牧場の生乳を使った濃厚なソフトクリームなど、茅ヶ崎産を全面に押し出す。その一方で、目指しているのは地域の住民にも楽しんでもらえる施設。観光客だけでなく、地元客も取り込むハイブリッド型が成功の秘訣と語る松本さん。進化を続ける道の駅のあり方とは?
人口2300人の小さな村を支える“日本一”の「道の駅」
京都府南山城村は人口約2300人、京都で唯一の村。宇治茶の主な産地でもある。そんな小さな村にあるのが、年間60万人が訪れる「道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村」。仕掛けたのは、駅長の森本健次さん。元々村役場の職員だったが、退職。退路を絶って道の駅づくりに奔走してきた。村で生産しているお茶「村茶」を活用した商品を開発し、道の駅をお茶尽くしにすることで、村茶のブランディングに成功。今では全国の道の駅ランキングで1位を獲得するほどに。森本さんにとって道の駅は村と村人のためのもの。お茶の収穫時期しか収入がなかった茶農家を支える存在に。村民による村民のための「道の駅」に密着する。
建設計画に住民が真っ二つ!「道の駅」は誰のためのものか…?
茨城県那珂市では、新たな道の駅の建設計画が進んでいる。市長肝入りで始まったこの計画では、地元農産物の直売所や農業体験ができるコーナーなどを中心に2028年に開業予定だ。総事業費は約30億円、そのうち約10億円は市の負担。市民の税金が投入されることになる。那珂市を訪ねるとこの建設計画を巡り、市民の意見が真っ二つに分れていた。人口減少が進む中、地元活性化の起爆剤に必要との声もあれば、失敗して負の遺産を残したくないという意見も。そんな中、このまま建設を進めることに納得のいかない有志たちが集まり、市や市議会に対し、説明会の開催を求めるなど、大きな反対運動が始まっていた。その一部始終に密着。果たして市民の願いは聞き入れられるのか?建設計画の行方は?
赤字続きの「道の駅」が閉館のピンチ!再建の秘策は!?
富山県南砺市の井波地区。250年続く木彫り彫刻が有名な場所だ。そこにある道の駅「いなみ 木彫りの里」。道の駅制度が始まった1993年より前からある“老舗”だ。その名の通り、施設内のいたるところに井波彫刻の木像が置かれるほか、彫刻総合会館も隣接している。井波彫刻の窓口やPRする役割も担っているのだ。そんな道の駅「いなみ」が閉館の危機を迎えていた。立地の悪さや、近年の団体客の減少などで慢性的な赤字。自治体からの補助金も打ち切られてしまっていた。そんな中、火中の栗を拾う形で7年前に駅長に就任したのが江尻大朗さん。レストランに爆盛りメニューや10段ソフトクリームなどを投入し、集客を工夫。徹底した経費削減などで赤字を減らしてきた。しかし、老朽化する施設を改修する費用はなく、このままでは集客の改善は望めず、黒字化も見通せない。そこで、江尻さんは最後のチャンスと大勝負に打って出た。ネットを通じて1000万円を集めるクラウドファンディングにかけることに。果たして道の駅を継続することはできるのか?そして地元の伝統工芸は守れるのか?